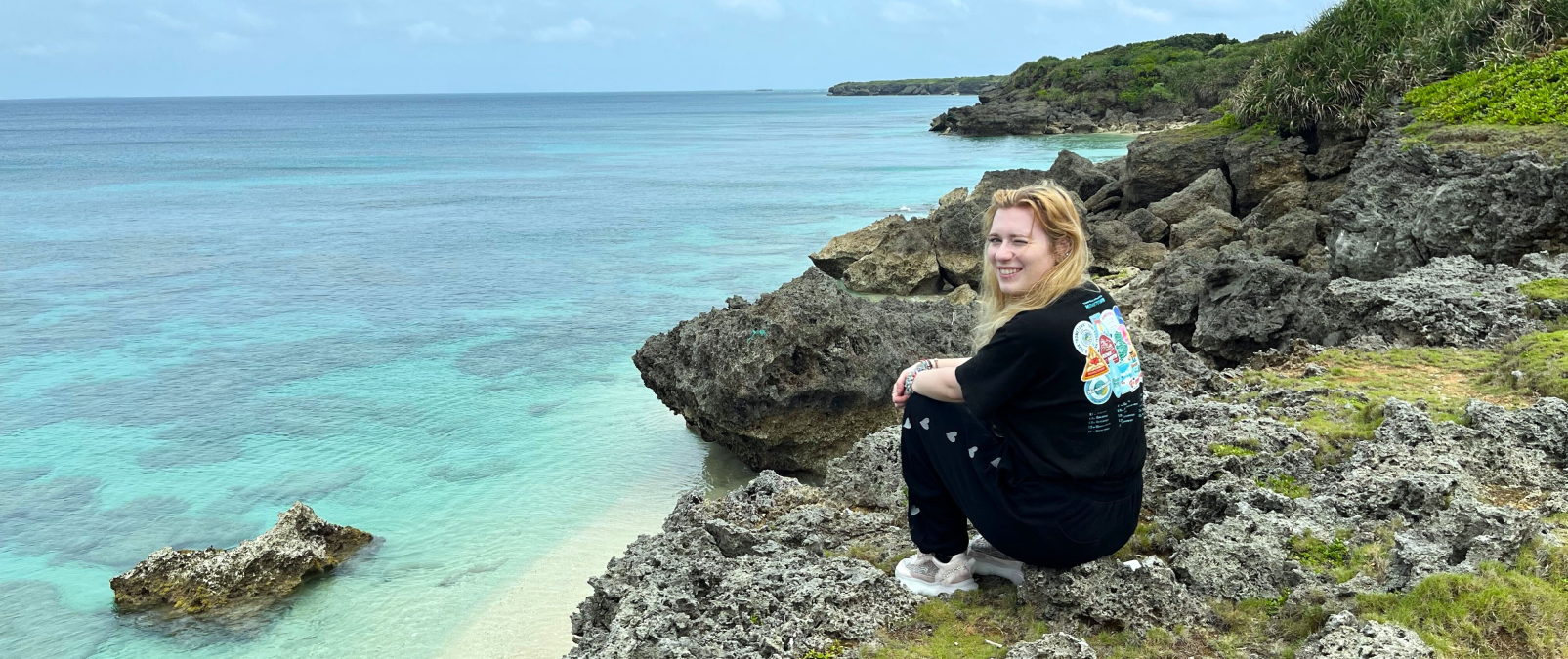

日本で自然と働くという夢を叶える──マロット・ルーシーの挑戦(前編)
科学と多様な人材の力で、自然と経済をつなぐ挑戦—シンク・ネイチャー
地球規模の環境問題が深刻化するなか、私たちは今、自然環境と経済活動の両立という難題に直面しています。従来の経済活動はしばしば自然資源を消耗させ、生物多様性を脅かすことがありました。しかし、持続可能な社会を築くには、自然と調和した経済活動への転換が不可欠です。
シンク・ネイチャーは、このような課題に取り組むために設立された会社です。最先端の科学的分析を駆使し、生物多様性を守りながらも経済活動を活性化させるソリューションを生み出すことを使命としています。その最大の特徴は、多種多様なバックグラウンドを持つ専門家が集結していることです。生物多様性など自然科学の研究者、コンサルタント、データサイエンティスト、経営管理のプロ、エンジニアなど、さまざまな分野から集まったメンバーがそれぞれの専門性を活かし、力を合わせて問題解決に挑んでいます。
本シリーズでは、シンク・ネイチャーの個性豊かなメンバーのストーリーを通じて、そのユニークな取り組みと魅力に迫ります。
日本で自然と働くという夢を叶える──マロット・ルーシーの挑戦(前編)
フランス出身のマロット・ルーシーは、世界各地で農業や自然と関わる活動に従事してきた。インドネシア、アマゾンの熱帯雨林、コーカサス山脈──さまざまな土地の人々と暮らし、自然の中で働いた経験は、彼女の生き方と価値観に大きな影響を与えている。

2024年、半年間のインターンとしてシンク・ネイチャー(以下、TN)に参加。その後、正式に社員として入社することが決まった。本記事では、インターンとしての経験とTNに出会うまでの背景を中心に、ルーシーの思想と実践を追う
自然とともにある暮らしから学んだこと
学生時代、ルーシーはジョージアやインドネシアの農村地域で数ヶ月間、地元のコミュニティと共に暮らした。資本主義的な暮らしとは違う、物や食の交換、自然との密接なつながりを体験したことで、自然と人間が調和した生き方が心の豊かさにつながることを実感した。

この経験を通して、彼女は自身の消費や食生活について深く考えるようになった。「動物の命を犠牲にしてまで食事をすることが自分には受け入れがたかった」と語るルーシーは、やがてヴィーガンとしての生活を選択するようになる。現在も、理想と現実のギャップに葛藤することはあるものの、「小さな行動が社会を変える土台になる」と信じ、自らの暮らしの中で持続可能性を実践している。
日本で自然と関わる仕事をする意味
日本への関心は幼い頃から抱いていたというルーシー。14歳ころから独学で少しずつ日本語を学び始め、2020年からは1年間、東京で日本語を本格的に学んだ。その後、AgroParisTechで学びながら自然と深く関わる仕事を探していたルーシーは、九州大学の研究室にインターン希望の問い合わせを送った。対応したのは、同大学で助教を務めると同時に、シンク・ネイチャーの取締役でもある楠本だった。

「国内外問わず、学生からの問い合わせ自体は珍しくないのですが、大学研究室にインターン希望というケースはとても稀でした。そこでTNを紹介したところ、予想以上に関心を持ってくれました。海外の学生が私たちの活動に興味を示してくれるのは率直に嬉しかったですね。特にルーシーさんほど積極的に反応して、実際に行動を起こす学生は初めてでした。日本とフランスのキャリアパスや仕事に対する柔軟性の違いを感じました」と振り返る。当初、メールでのやりとりはすべて英語だったため、オンラインミーティングでルーシーが流暢な日本語を話したことに驚かされたという。「その時、日本への深い興味と愛着を感じ、彼女なら日本語中心の業務も問題ないだろうと確信しました」とも語る。
TNのスタートアップならではの規模感やメンバー同士の距離感の近さ、多様なバックグラウンドを持つ社員が情熱的に働く姿に魅了されたルーシーは、「ここで働きたい」と直感したという。特にインターン先が沖縄に決まった際には、「海と森が共存する沖縄で自然と向き合う仕事ができるなんて運命的でした。これまでの経験をこの地で活かせることに大きな期待を抱きました」と語る。
インターン期間での成長と学び
インターン期間中、楠本はルーシーの適応力に感銘を受けたという。当初は基礎的なデータ入力を想定していたが、ルーシーの飲み込みが非常に早く、最終的には応用的な分析作業まで任せることができた。「彼女の仕事ぶりには驚かされました」と楠本は述べる。また、休日には積極的に地域のイベントに参加したり、日本の文化を楽しむ姿が印象的だったそうだ。

TNでのインターンを通じてルーシーは「設計」の重要性を学んだ。「農業と生物多様性の関係を定量的に分析する」ためのデータベース選択や検索キーワード設定など、方法論そのものを設計する重要性に気づき、厳密な計画がいかに成果に影響を及ぼすかを体験した。「今ではどんな作業も設計段階に一番時間をかけます」と語る。
今後の期待と展望
楠本はルーシーの将来に対して、「現在はサポート役が中心ですが、いずれは顧客課題の分析や解決策の設計を担ってほしい。日本育ちのメンバーにはない視点や価値観を持つ彼女は、今後TNが海外のクライアントや企業と協働する際に大きな強みになるでしょう」と期待を寄せている。
後編では、社員として新たなスタートを切ったルーシーの仕事内容やその視点の変化、そして今後の展望についてさらに掘り下げて紹介する。
