

「支える人」として、自然と社会をつなぐ──マロット・ルーシーの挑戦(後編)
科学と多様な人材の力で、自然と経済をつなぐ挑戦—シンク・ネイチャー
地球規模の環境問題が深刻化するなか、私たちは今、自然環境と経済活動の両立という難題に直面しています。従来の経済活動はしばしば自然資源を消耗させ、生物多様性を脅かすことがありました。しかし、持続可能な社会を築くには、自然と調和した経済活動への転換が不可欠です。
シンク・ネイチャーは、このような課題に取り組むために設立された会社です。最先端の科学的分析を駆使し、生物多様性を守りながらも経済活動を活性化させるソリューションを生み出すことを使命としています。その最大の特徴は、多種多様なバックグラウンドを持つ専門家が集結していることです。生物多様性など自然科学の研究者、コンサルタント、データサイエンティスト、経営管理のプロ、エンジニアなど、さまざまな分野から集まったメンバーがそれぞれの専門性を活かし、力を合わせて問題解決に挑んでいます。
本シリーズでは、シンク・ネイチャーの個性豊かなメンバーのストーリーを通じて、そのユニークな取り組みと魅力に迫ります。
「支える人」として、自然と社会をつなぐ──マロット・ルーシーの挑戦(後編)
インターンを経て、2025年に新卒社員としてシンク・ネイチャー(以下TN)に入社したマロット・ルーシー。現在はビッグデータ開発部の一員として、論文や報告書から生物多様性に関する情報を抽出し、誰もが活用できる形に整える仕事を担っている。
表舞台に立つことは少ないが、チーム全体を支える“土台”を整える役割に、彼女は大きなやりがいを感じている。
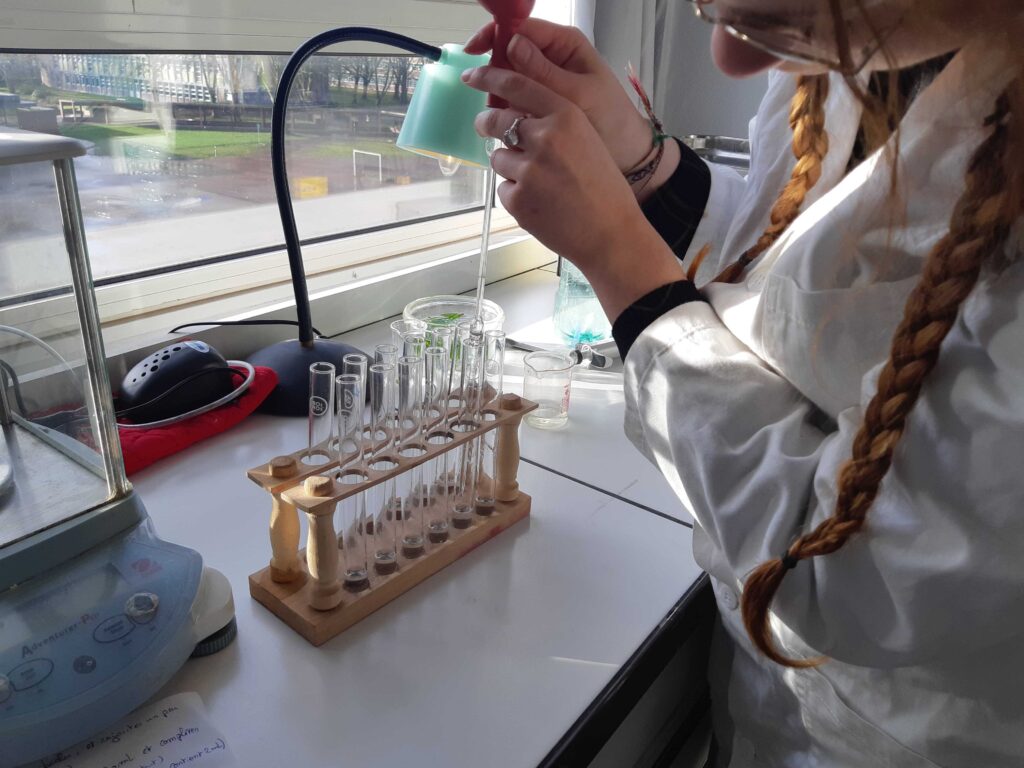
データを磨き、意味を編む日々
ルーシーが取り組んでいるのは、人間活動が影響を与えた地域とその周辺の自然環境について、生物の種や環境条件に関する情報を収集し、評価可能なデータとして整理する業務である。
「生物多様性に関するデータを多様な情報源から収集し、処理する業務を担当しています」
扱う情報は広範囲にわたる。鉱山復元に関する研究では、数年間の植生回復データを地図として再構築し、回復傾向を年単位で比較できるように整備した。また、製品のライフサイクル全体を評価するプロジェクトでは、鉱物採掘による環境・社会への影響を定量的に整理する作業を担当している。
Rを使った統計処理を学びながら、研究背景の整理や文献要約、プレゼン資料の作成までを幅広く手がける。
「数値だけを扱うのではなく、“なぜこうなったのか”を理解することが重要です。分析に入る前の設計と調査に、特に時間をかけるようにしています」
「見える」ようにするのは、地道な積み重ね
ルーシーの仕事は、いわば“情報を使える状態にする”裏方作業である。論文やソフトウェアから得られた生データを統一的な形式に変換し、誰もが安心して活用できる土台をつくる。
作業量が多いときには、入力チームと連携しながら、手作業とプログラムを行き来し、粒度を揃えた情報整理にあたる。
「自分が整えた情報が、誰かの仕事をスムーズにしている。そう思える日は、気持ちが明るくなります。自分の準備作業が同僚の業務に役立った時、とてもやりがいを感じます」 この姿勢は、インターン時代から一貫して変わらない。静かに、しかし確かに、チームの前進を支えている。

「生物多様性」との向き合い方
ルーシーの生物多様性への意識は、幼少期の体験から始まっている。8歳の頃、友達と花を摘んでいたときに「これも自然を傷つけることになるのでは」と気づき、守るための行動を始めた。ごみ拾いや昆虫の保護、川の調査やブログ発信など、仲間と立ち上げた小さな団体での活動は、環境に向き合う姿勢を決定づけたという。
その意識は国際的な経験を重ねるなかでさらに広がった。フランスでは意見を発信する文化が根づき、環境問題も日常的に議論される。一方で日本では、人々が協力的に行動する姿勢が強く、その点に大きな敬意を抱く。ただ同時に、課題が見過ごされてしまう場面もあり、両国の違いから学ぶことは多いと語る。
そして現在の暮らしでも、そのスタンスは揺らがない。ヴィーガンとして動物や環境に配慮しながら暮らす中で、日本ではリサイクルや食品の選択肢が限られており、葛藤を覚えることも少なくない。それでも「小さな行動が大きな変化につながる」と信じ、日常の一つひとつの選択に生物多様性への思いを込めている。

「伝える」は、科学と社会の橋渡し
異なる文化や背景を持つ人にどう届けるか──これは、自身が海外での生活を通して繰り返し向き合ってきた問いでもある。科学を社会につなぐ“橋渡し役”としての視点が、彼女の仕事に深みを与えている。
最後に、これからの目標について尋ねると、ルーシーは静かに、しかし迷いなく答えてくれた。
「これからも、“役に立てるデータ”を丁寧につくっていきたいです。もし将来フィールドに出る機会があっても、TNで学んだ“問いの立て方”や“背景を理解する姿勢”を持ったまま、自然と関わっていきたいと思っています」
